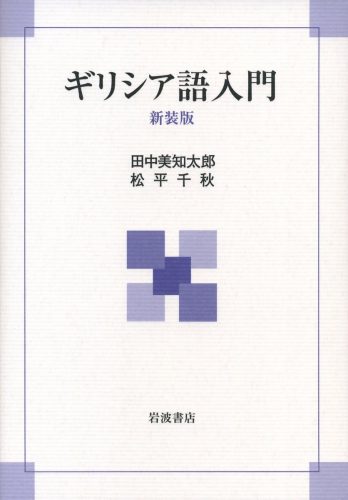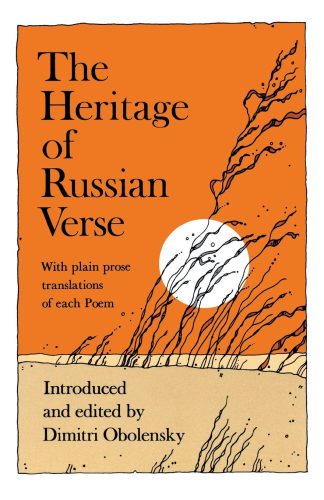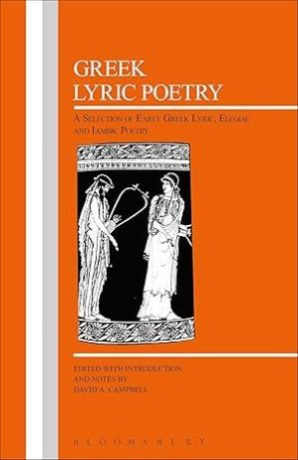近藤 明子
「おめでとうございます。」と山下太郎先生がおっしゃった。『ラテン語初歩』(田中利光/著・岩波書店)の巻末最後の文例を読み通したのだ。テキスト一冊上がり、ということだ。
「ありがとうございます。」──この紙上では嬉しい気持ち、先生、夫、家族、友達、皆さんのおかげです! 的な感想がふさわしい、が、しかし、正直、達成感どころではないのだ。
昨春、お山の学校の案内を見て、珍しい「ラテン語」に飛びついた。私はヨーロッパの中世・ルネッサンス期の音楽が好きだ。このあたりの歌は大半がラテン語かそこから派生した言語で書かれている。音楽と時代の人の体温を感じたい、その方法のひとつが、彼らの使った言葉を知ることであるのは言うまでもない。既にある日本語訳では受け取ることのできない何かがある、それが欲しい。
文法がわかったら辞書を引き引き読めるだろう。文法さえ……。
初めのうち、主語がなくても行動の主体がわかる、つまり、 amo te の二音節で、私はあなたを愛している、と言い切れる直感的な言葉は快かった。が、テキスト半ばから、活用の多さ、あまりに融通のきく語順、日本語に置き換えられない感覚に、硬い頭はパニックに陥った。そんな時……。
Dimidium facti qui coepit habet. (ホラティウス『書簡詩集』)
(事を始めた人は、事の半分をすでに成し遂げたのである。)
34課に登場する文例だ。何と! それでは行くも帰るも同じ距離、ならば先方へ!
テキストの著者は絶妙に攻めてくる。各課末尾の文例が心をくすぐる。さらに、最終課の読み物は辞書で日本語に変換できたとしても、それが何を言わんとするのか考えることなしにはちんぷんかんぷんのままであるが、先生に導かれながら訥々と稚拙な訳をし、それを叩き台に内容を深めて頂くと、時折書き手の叡智や言葉の妙技にはまるように思えることがある。(私の稚拙さに忍耐強く時間を割いてくださった先生に感謝!です)それでもお山を降りながら、やっぱりまだ何もわかっていないと自覚する。
今や、文法さえ……ではない。言葉を受け取ることもままならない。受け取れるようになりたい、と希う。希いが背中を押してくれる。
ペトラルカというイタリア中世末期の詩人がいる。ルネッサンス運動の主唱者の一人だ。その書簡集(近藤恒一/訳・岩波文庫、原文はラテン語)を聞くと私の憧れる時代がリアルタイムで述べられている。そしてペトラルカ自身は焦がれる想いで古代ローマ文化への憧れを全篇に熱く語っている。彼はフォロ・ロマーノに立ちすでに廃墟となった遺跡の前で感激している。それを読みながら、私はまた、私の動揺を感じる。
「憧れの連鎖、ですね。」と先生が言葉にしてくださった。連鎖の片端に手をつないでいるという感覚は、自分の居場所が保証されるような安らかな思いと、憧れをまた誰かに伝え渡していけたら、というわくわくする思いとを与えてくれる。憧れで心を満たすのは心地よく、ラテン語を学び続けることは、憧れへの扉を開く鍵のひとつなのだ。その鍵ひとつを得ようと四苦八苦している私には、正直、達成感どころではないのだ!
(2004.10)