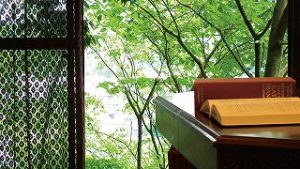

今日は将棋道場がありました。予想を上回る参加があり、教室中が熱気に包まれました。
はじめの挨拶で、Ryoma 先生が「将棋で強くなるには礼を重んじることが大切」ということを話されたのが印象に残っています。
私は用事があり途中退席しましたが、聞くところでは白熱した試合が相次いだようです。「勝っておごらず、負けてひがまず」これからも和気藹々と将棋道場が回を重ねますように。
山の学校は小学生から大人を対象とした新しい学びの場です。子どもは大人のように真剣に、大人は子どものように童心に戻って学びの時を過ごします。
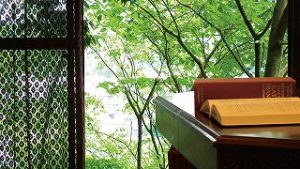

今日は将棋道場がありました。予想を上回る参加があり、教室中が熱気に包まれました。
はじめの挨拶で、Ryoma 先生が「将棋で強くなるには礼を重んじることが大切」ということを話されたのが印象に残っています。
私は用事があり途中退席しましたが、聞くところでは白熱した試合が相次いだようです。「勝っておごらず、負けてひがまず」これからも和気藹々と将棋道場が回を重ねますように。
参加してくれた小学生たちの雰囲気から、まず第一に肌で感じたのは、将棋に対する「憧れ」です。
それが「嬉しいなあ」と感じました。
>はじめの挨拶で、Ryoma 先生が「将棋で強くなるには礼を重んじることが大切」ということを話されたのが印象に残っています。
そんなこともあえて言わせてもらいましたね^^
改めて思うのですが、将棋が強くなる秘訣は、
最初の「よろしくお願いします」
最後の「参りました」「負けました」
そして間の姿勢を正しくすること。
この3つができていれば、おのずと強くなると思います。
姿勢は、意識しなければ保てないものです。ということは、それだけ「強くなりたい」という気持ちがそこにはあらわれています。いわば試金石です。姿勢がしっかりしていれば、一局一局を大事に思うことができますし、そうやって大事に思ったことには集中します。集中すれば、おのずと上達します。私などは全然強くないのですが、それだけは思います。
あとは「負けたときに、どれだけ悔しいと思えるか」でしょうか。「悔しがれること」も才能のうちだと思います。
そして、勝つための努力としては、「詰め将棋」が最初で最後です。これは一人でもできるので、ぜひお勧めです…というよりは、将棋というものの本質(王を詰めること)なので、これを避けては絶対に強くなれないものが将棋であるはずです^^
さて、『山びこ通信』の末尾に小さく載っていますが、次回は4月19日(4:00~6:00)を予定しています。ぜひふるってのご参加をお待ちしています^^/
かけつけて下さった先生方も、ご父兄の方も、どうもありがとうございました。
昨日はご苦労様でした。盛況だったようですね。亮馬先生がずいぶん以前に山の学校に持ってきてくださった将棋板は昨日出番があったのでしょうか。(cf. http://www.kitashirakawa.jp/taro/yama/archives/000578.html)
勝負事は勝つか負けるかしかありません。どんなに強い人も負けることを経験しない人はありません。亮馬先生が書かれたように、「負けたときに、どれだけ悔しいと思えるか」は、私も大事なポイントだと思います。
逆説的ですが、この悔しさは自信を育てる源です。「悔しい」と思えるのは、自分はもっと出来るはず、という気持ちがあるからです。
イソップの酸っぱいブドウのように、この気持ちをあれこれ言い訳してごまかすことは避けたいです。でないと、せっかく勝負した経験が無駄になります。
次回の日程は4月19日ですね。またたくさんの豆棋士に出会えることを楽しみにしています。
>ずいぶん以前に山の学校に持ってきてくださった将棋板は昨日出番があったのでしょうか。
あ、ありました。
脚を取って、盤だけにした状態でお目見えしています^^
囲碁盤もほしいですね(笑)。
昨日は初めて山の学校のイベントに参加させて頂きました。
予想していた以上にたくさんの小学生たちが集まっていて、そして皆それぞれに将棋を楽しんでくれていて、大成功だったのではないかと思います。
あんなに元気な将棋道場は初めてでした(笑)
僕も久しぶりに将棋を指す経験ができて、楽しませてもらいました。
卓佐くんには豪快に負けてしまいましたが、次回の将棋道場までに僕ももう少し勘を取り戻してきたいと思います。
また次の将棋道場も参加させて頂こうと思いますので、よろしくお願いします。
昨日は亮馬先生のほかに、百木先生、浅野先生がご参加くださり、大いに盛り上がりました。今、一年、二年の子どもたちも、回を重ねるうちに、いずれ中学生になるでしょう。そのころには、とんでもなく、層の厚い将棋道場になっていることでしょう。植物の成長と同じで、今は土の中に眠っている子どもたちですが(卓左君を除く)、いずれ芽が出、花が咲くときが訪れると思います。今後とも、長い目でご指導をお願いいたします。